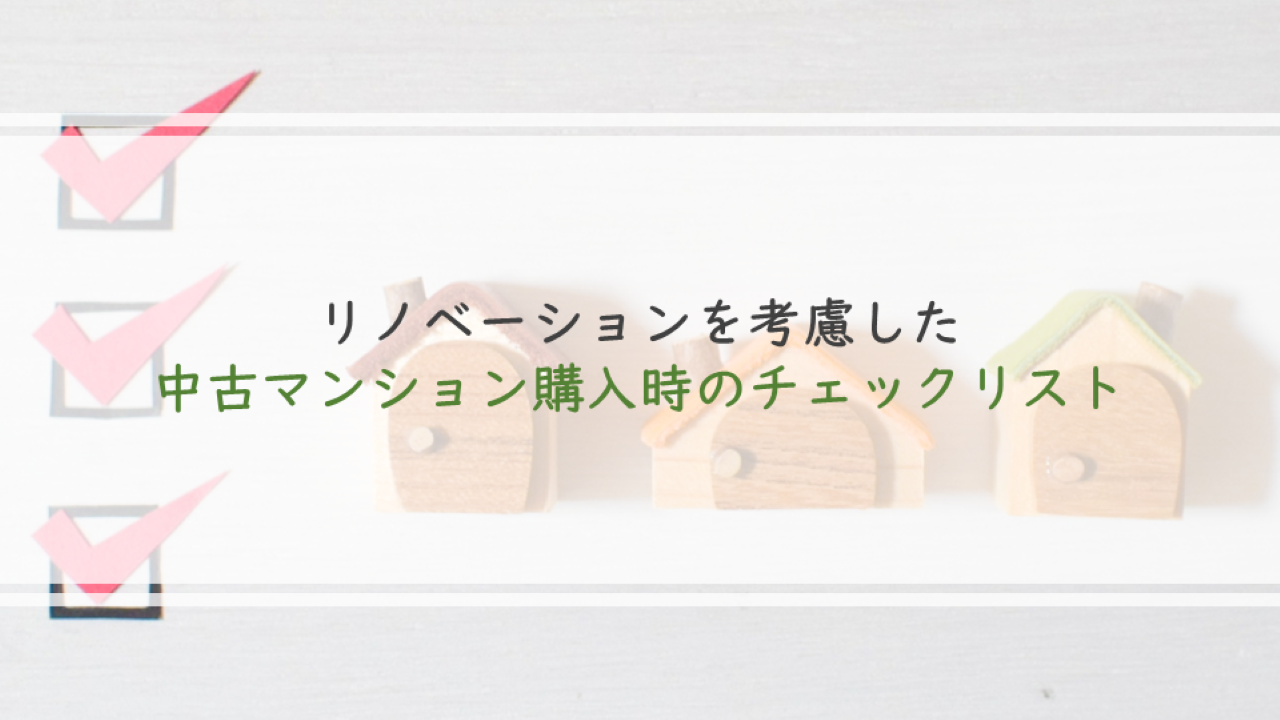
リノベーションを考慮した中古マンション購入時のチェックリスト
近年、新築マンションの価格高騰により、「中古マンションを購入してリノベーションする」という選択肢が注目されています。中古物件であれば、新築よりもコストを抑えつつ、間取りやデザインを自由にカスタマイズできる点が大きな魅力です。さらに、立地の選択肢も広がり、資産価値の高い物件を見つけやすくなるというメリットもあります。
ただし、物件選びを誤ると、「希望通りのリノベーションができない」といった失敗につながることもあります。そこで、購入前に確認すべきポイントを整理したチェックリストを活用することで、理想の住まいを手に入れやすくなります。
建物の構造や耐震性をチェック
建物の構造や耐震性は、最も重要なチェックポイントの一つです。
どんなに内装をおしゃれにできても、建物自体に問題があれば、安心して長く住むことはできません。ここでは、構造の違いや耐震基準、資産価値に影響する4つのポイントを詳しく解説します。
① マンションの構造の種類と耐久性のポイント
マンションの構造には、大きく分けて3種類あります。それぞれの特徴を理解し、リノベーションのしやすさも考慮して物件を選びましょう。
RC造(鉄筋コンクリート造)
・コンクリートと鉄筋を組み合わせた構造で、耐震性・耐火性に優れている
・一般的な中高層マンションに多く採用されており、リノベーションの自由度も高い
・遮音性が高いため、生活音が響きにくい
SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)
・RC造に鉄骨を加えた構造で、さらに強度が高い
・高層マンションに多く使われ、地震や台風にも強い
・構造が複雑なため、リノベーション時の解体・改修が難しく、費用が高額になる場合がある
木造
・低層のマンションやアパートに採用されることが多い
・通気性が良く、調湿機能があるものの、RC造・SRC造に比べると耐久性・耐火性は劣る
・構造的にリノベーションしやすいが、耐震補強が必要になることもある
マンションのリノベーションを前提にする場合は、RC造が最もバランスが良く、自由度も高いため人気です。SRC造は耐久性が高いですが、間取り変更が難しいケースもあるため注意が必要です。
② 耐震基準改正について
日本では、大地震の経験をもとに建築基準法の耐震基準が何度も改正されてきました。中古マンションを購入する際は、物件がいつ建てられたものかを確認し、耐震基準に適合しているかをチェックすることが大切です。
1981年:新耐震基準の導入
・それ以前の「旧耐震基準」では、大地震に耐える設計ではなかった
・1981年6月1日以降に建築確認を受けた建物は、新耐震基準に適合
・震度6〜7クラスの地震でも倒壊しない構造が求められるようになった
2000年:耐震基準のさらなる強化
・柱や壁のバランスの強化、地盤の考慮が義務付けられた
・木造住宅の耐震基準も強化され、より安全性が高まった
・1981年以降の建物でも、2000年以降の物件のほうがより安心
上記を踏まえ、1981年以前の建物は、耐震補強がされているかのチェックが必要です。
また、できるだけ2000年以降の建物を選ぶのが安心と言えるでしょう。
③ 築年数と資産価値の関係
築年数が古いと「資産価値が低くなる」と思うかもしれませんが、築古でも価値が落ちにくい物件の条件を紹介します。
・ 立地が良い(駅近、人気エリア)
・管理が行き届いている(修繕計画がしっかりしている)
・新耐震基準(1981年以降)の物件
・リノベーションの自由度が高い(スケルトン工事が可能)
築年数が古いからといって、一概にデメリットとは限りません。管理状態や耐震性、リノベーションのしやすさを重視して選ぶことが大切です。
④ 建物の劣化診断のポイント
物件を選ぶ際は、外観や共有部分の状態もしっかりチェックしましょう。
以下のポイントを確認すると、建物の劣化具合を判断できます。
・外壁のヒビ割れやタイルの浮き → 建物の構造に影響がある可能性
・鉄部のサビ(階段や手すりなど) → 適切なメンテナンスがされていない可能性
・エントランスや共用廊下の清潔さ → 管理状況を把握できるポイント
・配管の劣化(錆びや水漏れ) → 給排水トラブルのリスク
築年数が古くても、管理がしっかりされている物件は良好な状態を保っている場合もあります。劣化状況を事前にチェックすることで、後々の修繕コストを抑えることができます。
リノベーションを成功させるためには、建物の構造や耐震性をしっかり確認し、安心して長く住める物件を選ぶことが何より重要です。
共有部分と専有部分の違いを理解

中古マンションのリノベーションを考える際、「どこまで変更できるのか」を事前に把握することが重要です。マンションには、自由にリノベできる専有部分と勝手に変更できない共有部分があり、管理規約によって制約が異なります。
ここでは、リノベーションの範囲や注意点を詳しく解説します。
① マンション管理規約をチェック
マンションには住民の快適な生活を守るための「管理規約」があり、リノベーションできる範囲や禁止事項が決められています。
例えば、室内の壁・天井・床の変更やキッチン・浴室の設備交換は可能ですが、窓や玄関ドア、バルコニー、共用部分の配管・排水管は勝手に変更できません。
さらに、防音対策のルールや工事可能な時間帯など、使用細則も事前に確認することが重要です。
② 排水管の制約をチェック
キッチンや浴室を移動する際は、排水管の位置が重要なポイントになります。
「床上排水(配管が床の上を通るタイプ)」なら比較的移動しやすいですが、「床下排水(配管が床の下を通るタイプ)」だと制約が多く、勾配の確保も必要です。
また、共用部分の配管を変更する場合は管理組合の許可が必要なため、事前に管理規約を確認し、専門家に相談しましょう。
③ 意外と知られていない窓・玄関ドアのルール
窓や玄関ドアは建物の外観に関わるため、共用部分として基本的に変更不可です。
ただし、玄関ドアの内側のみリフォーム可能なケースや、防音・断熱目的の二重サッシ設置が認められる場合もあります。
実はバルコニーや専用庭の改装も管理規約で制約されている場合が多いため、必ず確認が必要です。
④ 管理組合との交渉の仕方(変更申請の流れ)
リノベーション内容によっては管理組合への「変更申請」が必要です。
まず管理規約を確認し、施工業者と工事計画を作成した上で、管理組合に申請を提出します。審査には約1〜2ヶ月ほどかかるため、特に水回りの変更や防音対策工事は早めの相談が重要です。承認後は規定を守って工事を進めましょう。
マンションのリノベーションは自由度があるようで意外と制約も多いため、事前の確認が成功のカギになります。
リノベーション費用と可能性を見極める方法
この章では、費用の違いや、リノベーションに適した物件の選び方、高額になりやすいリノベーション内容について解説します。また、補助金や減税制度を活用したお得なリノベーション方法についても紹介します。
① フルリノベーションと部分リノベーションの費用比較
フルリノベーションは、内装・設備・間取りの大幅な変更を含むため、費用が高額になります。一般的には、100万円〜1000万円以上が必要で、規模に応じて価格が変動します。大きな工事が必要なため、工期も長く、期間中の仮住まいや一時的な生活環境の変更も考慮する必要があります。
一方、部分リノベーションは、主にキッチンや浴室のリフォーム、壁の塗装、床の交換などにとどまり、比較的安価に実施できます。費用は30万円〜500万円程度と、フルリノベーションよりもリーズナブルですが、理想的なデザインや機能にするための工夫が必要になります。
② リノベーション向き物件の条件
リノベーションを成功させるためには、物件選びが重要です。特に、スケルトンリフォーム(全ての壁を取り払い、骨組みだけにする工事)を行いたい場合、壁や床がすでに十分に強固であることが望ましいです。壁が薄すぎたり、柱が不安定だったりする物件では、リノベーションの難易度が上がり、追加費用がかかることもあります。
また、リノベーションを行いやすい物件は、構造がシンプルで、あまり手を加える必要のない設備や配管が整っていることも大切です。購入前に専門家に診断を依頼し、物件の状態やリノベーション可能な範囲を確認しておくことがポイントです。
③ 水回り・間取り変更のコストが高くなるケース
水回りや間取りの変更は、リノベーション費用の中でも特に高額になることが多いです。キッチンや浴室の移動やトイレの位置変更などは、排水管や給水管の配置を見直さなければならないため、配管工事が必要です。これに伴い、床の解体や壁の開口作業、さらには防水工事なども加わり、費用が大幅に増える場合があります。
また、間取り変更に関しても、壁を取り払う大規模な工事を行う場合、構造体に影響を与えないよう慎重に計画しなければならないため、設計費用や施工費用が高くなることを理解しておくべきです。水回りや間取り変更を希望する場合、事前に十分な予算設定と計画を立てておくことが重要です。
④ 補助金・減税制度の活用
リノベーションには、補助金や減税制度を活用することで、費用負担を軽減する方法があります。例えば、省エネリノベーションやバリアフリー改修に対しては、国や自治体からの補助金が支給されることがあります。これらの補助金を活用することで、リノベーション費用を数十万円以上抑えることが可能です。
さらに、住宅ローン減税や耐震リフォームに対する税制優遇も利用する価値があります。特に、耐震基準のクリアや省エネ機能を強化する場合は、税金の控除を受けることができるため、リノベーション費用全体をお得に進めることができます。
補助金や減税を利用するためには、各制度の申請方法や条件をしっかりと確認し、リノベーション計画に組み込むことが重要です。
購入前に不動産会社と相談すべきポイント

物件探しの段階から不動産会社としっかり相談することが大切です。不動産会社のアドバイスを受けることで、スムーズに計画が進められます。この章では、不動産会社と相談すべき重要なポイントを解説します。
① 「リノベーション向き物件」に強い不動産会社を選ぶ
物件探しの際、リノベーションの知識がある不動産会社を選ぶことが重要です。
リノベーション実績が豊富な不動産会社や、リノベーション会社と提携している不動産会社を選ぶと、物件の状態やリノベーションの可能性について的確なアドバイスを受けることができます。
また、物件情報を見る際には、管理規約や耐震基準、配管の状況など、リノベーションに影響する部分をきちんと確認できる会社を選ぶと安心です。
② 仲介手数料・諸費用も含めた総予算の考え方
中古マンションを購入する際は、物件価格だけでなく、仲介手数料や登記費用、ローンの諸費用などの追加コストも考慮しなければなりません。
一般的に、物件価格の7〜10%程度が諸費用としてかかるため、総予算を考える際に忘れないようにしましょう。
また、リノベーション費用も含めた資金計画を立てる際は、どの部分にどれくらいの費用がかかるのかを明確にすることが大切です。
③ インスペクション(住宅診断)の活用でリスクを減らす
リノベーションを前提に中古マンションを購入する際は、インスペクションを活用することで、建物の状態を把握し、リスクを減らすことができます。インスペクションとは、建物の構造や劣化状況、給排水管の状態などを専門家が調査し、リノベーションが可能かどうかを診断してくれるサービスのことです。
特に、築年数が古い物件の場合は、給排水管の老朽化や耐震性の問題があるケースもあるため、購入前にインスペクションを依頼しておくと安心です。
④ 物件価格+リノベーション費用の住宅ローンを組む際のポイント
中古マンション購入とリノベーションを同時に行う場合、「リノベーション一体型ローン」を利用すると、物件購入費用とリノベーション費用をまとめて借りることができます。このローンを活用することで、リノベーション費用を自己資金で用意する必要がなく、月々の支払いを安定させることが可能になります。
ただし、通常の住宅ローンとは異なり、リノベーションの具体的なプランや見積もりを事前に提出する必要があるため、リノベーション会社と協力しながら計画を立てることが大切です。
リノベーション市場の最新動向をチェック
リノベーションする人が増えてる背景には、新築価格の高騰や住宅に対する価値観の変化があります。また、コロナ禍を経て「自分好みの住まいを作りたい」というニーズが高まり、リノベーション市場はさらに拡大しています。ここでは、最新の市場動向について解説します。
① 中古×リノベーション市場拡大の背景
新築マンションの価格は年々上昇し、都心部では購入が難しい状況が続いています。そのため、中古マンションを購入してリノベーションすることで、コストを抑えながら理想の住まいを実現する人が増加しています。
さらに、コロナ禍以降、リモートワークが普及し、「在宅時間を快適に過ごせる住まい」への関心が高まりました。これにより、間取り変更やデザイン性の高いリノベーションの需要が増加し、リノベーション市場は活況を呈しています。
② 人気エリア・物件の傾向
最近の傾向として、都心部の駅近物件が人気ですが、テレワークの普及により、広さを優先した郊外の物件を選ぶ人も増えています。
・駅近派:利便性を重視し、築年数が古くても好立地の物件を選ぶ
・ 広さ重視派:都心から少し離れても、広めの間取りを確保できる物件を選ぶ
また、リノベーション向きの「スケルトンリフォームがしやすい物件」も注目されています。
特に、築20〜40年のマンションはリノベーション前提で購入されるケースが多いです。
③ 住宅政策の影響と今後のリノベーション需要
政府も中古住宅の流通促進を進めており、リノベーションに関する補助金や減税制度が充実しています。
たとえば、「長期優良住宅化リフォーム補助金」や「住宅ローン減税」などが活用できるため、今後もリノベーション市場の成長が期待されています。
また、SDGsや脱炭素の観点から、既存住宅を活用する「サステナブルな住まいづくり」の意識が高まり、エコリノベーションや断熱改修のニーズも増加すると考えられます。
リノベーション市場は、新築価格の高騰やライフスタイルの変化により、今後も拡大が見込まれます。立地重視か、広さ重視かの選択肢が広がり、住宅政策の後押しも追い風となっています。
最新の市場動向を把握しながら、自分に最適なリノベーション計画を立てましょう。
初めてのリノベーション・リフォームガイド

リノベーションは自由度が高い一方で、計画や業者選びを間違えると、コストオーバーや工期の遅れにつながることもあります。
① リノベーションを成功させるためのスケジュール例
リノベーションは、計画から完成まで約4〜6ヶ月かかるのが一般的です。以下の流れを参考に、スムーズに進めましょう。
スケジュール例(6ヶ月前から準備)
・6ヶ月前:物件探し・資金計画を立てる
・4〜5ヶ月前:施工会社・設計士と相談、プランを決定
・3〜4ヶ月前:見積もり&契約、住宅ローン申請
・2ヶ月前:工事開始(工期は2ヶ月前後)
・完成:最終チェック&引き渡し
特に、施工会社との打ち合わせやローン申請には時間がかかるため、早めに準備することが大切です。
② 業者選びのコツ(施工会社・設計士・デザイナーの役割)
リノベーションでは、複数の専門家と協力することが成功のカギです。
・施工会社:実際に工事を担当。実績のある会社を選び、見積もりを比較する
・設計士:間取り変更やデザインを考案。自分の理想を明確に伝えることが重要
・デザイナー:素材選びや空間の演出を担当。好みのテイストに合ったデザイナーを探す
業者によって得意分野が異なるため、施工実績や口コミを確認し、相性の良い会社を選ぶとスムーズに進められます。
③ 失敗しがちなポイントと回避策
リノベーションでは、以下のような失敗が起こりやすいため、事前に対策を考えておきましょう。
・コストオーバー → 事前に予算に対して+10〜20%程度の余裕を持つ
・工期遅延 → 余裕のあるスケジュールを組む&進捗を確認
・希望通りにならない → イメージを具体的に伝える(写真・資料を活用)
特に「追加工事」が発生しやすいため、見積もりの段階で詳細な費用を確認することが重要です。
しっかり計画を立てることで失敗を防ぎ、満足度の高い住まいを実現できます。
スケジュール管理や業者選びを慎重に行い、予算オーバーを防ぐ工夫をしながら進めることが成功のカギです。自分に合った方法で、理想のリノベーションを叶えましょう。
まとめ
中古マンションの購入とリノベーションを成功させるためには、物件選び・予算計画・信頼できる施工会社選びの3つのポイントを押さえることが大切です。事前に建物の構造や耐震性、管理規約を確認し、リノベーション費用をしっかり見極めることが、スムーズな進行へとつながります。そして、リノベーションにおいて最も重要なのは、信頼できるパートナー選びです。
リバータスでは、リノベーションに関わる多岐にわたる工程を一括で請け負い、低コストで高品質なサービスを提供します。お客様のニーズやこだわりに応じて、物件の新たな価値を創出し、住まいをより快適で安心できる空間へと生まれ変わらせます。
理想の住まいを実現するため、ぜひお気軽にご相談ください。
